ハンセン病のこと

全国には14のハンセン病国立療養所があり、そのうちの一つ、「多磨全生園(たまぜんしょうえん)」が東村山市にあります。武蔵野うどんや地域で活躍している人たちなど、まちのいいもの・大事なことをお伝えする『たまきた』ですが、北多摩地域におけるハンセン病の歴史も「大事なこと」だと考え、取材を開始することにしました。
ハンセン病とは
ハンセン病(Hansen’s disease)は、らい菌(Mycobacterium leprae)によって引き起こされる慢性の感染症です。皮膚・末梢神経・粘膜を中心に感染し、進行すると手足のしびれや変形、皮膚の斑点や潰瘍などの症状が現れます。特に末梢神経が冒されることで、感覚が鈍くなるのが特徴です。
感染と治療
感染経路:主に長期間の密接な接触による飛沫感染と考えられています。ただし、感染力は非常に弱く、普通の生活ではうつりません。
潜伏期間:数年~10年以上と長く、発症に気づきにくいことがあります。
治療法:現在では多剤併用療法(MDT)によって、完治が可能な病気です。1980年代以降、治療が世界中に普及しました。
なぜ差別が起きたのか?
かつてハンセン病は「不治の病」「遺伝病」と誤解され、感染者は強い偏見の対象となりました。日本では1907年に「癩予防法(らいよぼうほう)」が制定され、患者は強制的に隔離されました。
治療法が確立された後も隔離政策は続き、1996年にようやく廃止。その後、2001年には元患者による国家賠償請求訴訟で、国の責任が認められました。
現在の状況
日本では毎年数名の新規患者が報告される程度で、すべて輸入例(海外で感染)です。早期発見・治療により、後遺症を残すことなく治せる病気になっています。しかし、長年の差別と隔離の歴史により、元患者やその家族は今も社会的偏見や苦しみと向き合っています。
名前の変遷と今後
かつて「らい病」と呼ばれていたこの病は、ノルウェーの医師アルマウェル・ハンセンによる病原体の発見にちなみ、現在は「ハンセン病」と呼ばれるようになりました。
この名称変更は、差別的な響きを避けるためでもあります。今後も、ハンセン病に対する正しい理解と、人権の尊重が求められています。
今後、北多摩エリアで記していくべき歴史として、ハンセン病について取材をしていきます。
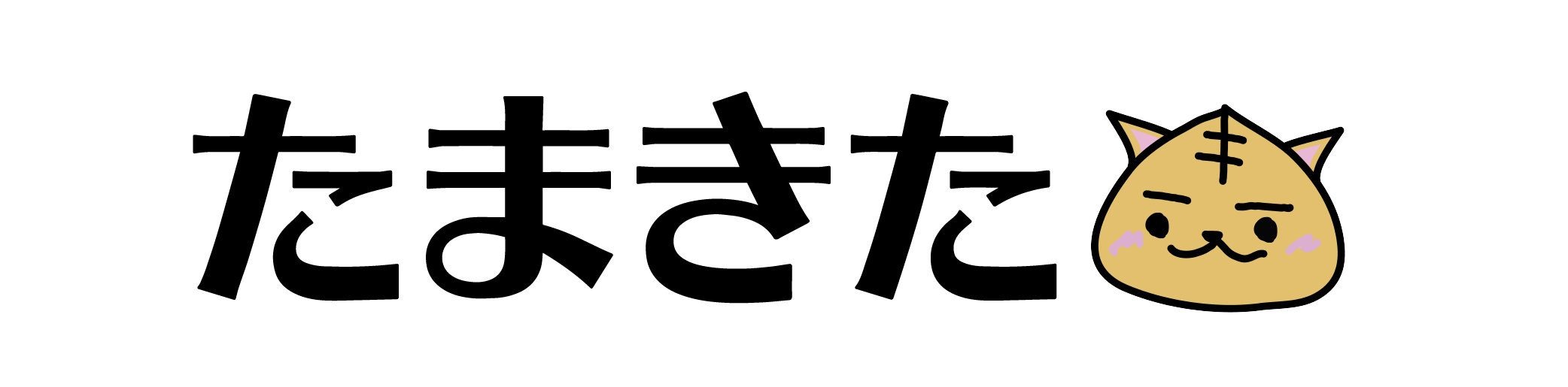
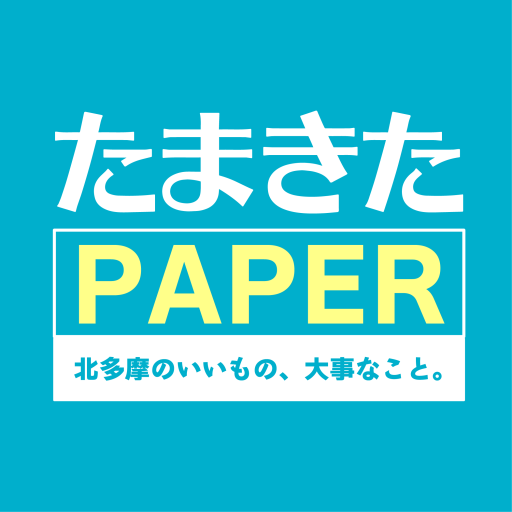

映画、砂の器もこの病気からの悲しいお話でした。
近くにありながら、まだ行ったことがありません。
もう少し涼しくなったら、出かけてみようと思っています。
チロルンまみーさん
コメントありがとうございます。砂の器も悲しいお話ですよね。よく調べないままに偏見を持つことの残酷さを感じます。広々として、静かな迫力のある場所だと思います。ぜひ、行ってみてください。